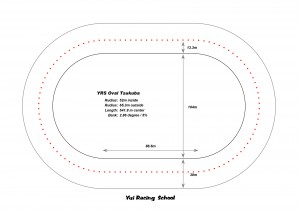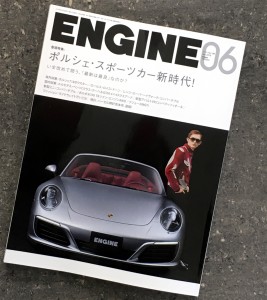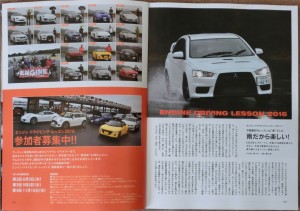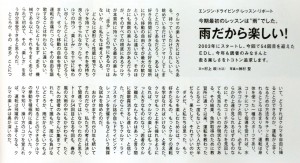第192回 レースで腕を磨く
ユイレーシングスクールは卒業生を対象にレースを開催している。レースと言ってもライセンスも要らないし、ふだん乗っているクルマで参加できるし、観客もいないから、日本で一般に認識されている自動車レースとは少しばかり趣きが違うかも知れない。
しかし、『クルマを道具として用い、速さを勝敗の要因とする競技』という自動車レースの定義からすれば、れっきとしたレースだ。しかも知っている人は知っているけど、YRSスクールレースの常連はレベルが高くしぶとい。
なので、手軽に参加できる割に敷居が高いのだろうか、新規の参加者がなかなか増えない。そこで、6月と7月にレースデビューキャンペーンをやることにして、初めてYRSオーバルレースに参加する人には参加費大幅割引の特典を用意した。
で、6月のレースには4名のYRS卒業生がレースデビューを果たした。ユイレーシングスクールはレースに出ることもドライビングテクニックの向上に役立ちます、といつも言っているけれど、実際に初めてレースに参加した当人がどう思っているか、感想文を読んでもらったほうが手っ取り早い。今回は2名の方が送ってくれた。
・Mさん 51歳 VWポロ
今回、YRSオーバルレースを大変楽しませて頂きました。オーバルレースと言えばインディ500とかありますが、今まで全く興味なかったんですよ。それよりルマンとかニュル耐久レースの方が本物のレースと思っていました。がしかし、目から鱗でした。やはり食べず嫌いではダメですね。以下、私の感想です。
‐ まず、今回初めて参加の人達に、参加費用含めてハードルを下げて頂いたので気軽に参加できました。他の初めて参加者の方たちも同様のコメントされてました。従いまして、間口を広げるために継続されてはいかがでしょうか。
‐ いつも前後左右に車がいるため、常に360度注意を払いながらドライブをするよいレッスンになりました。
‐ 他の車がいつも近くにいるので相手との駆け引きみたいな状況が生まれて、考えてドライブする癖をつけるよいレッスンだと思いました。
‐ 相手が差し迫るとミスしがちですが、レースでもメンタルを冷静にする必要がありますね。勉強になります。
‐ サーキットの走行枠で走るのと違い、相手がいるので時にドライブのセオリーを無視した状況下に陥ることもままありましたが(コーナーで鼻先を先に入れたいがために突っ込み過ぎるとか)それも含めてレースなのかなと面白かったです。
‐ 車の性能差を気にせずレースが出来る安心感がありました。
‐ アイドルタイムが少なく多くのセットを周回出来るので、費用対効果大と感じました。(普通の走行会やレースだと20-30分2本とかで費用も高い)
‐ やはりFMラジオを通じてリアルタイムにアドバイスを頂けるのがためになります。(後でこうでしたよと言われても、もう忘れている場合がほとんど)
‐ みなさん、レースとはいえマナーが大変良いと感じました。私が参加する走行会では赤旗や、強引なせめぎあいなど気分を悪くするケースが多いのですが、それが無さそうですね。サーキットでのレースになれば変わってしまうのかもしれませんが。
‐ 都合が合えば、また参加したいと思います。
‐ オーバルのみならず、FSWのショートコースや筑波1000あたりでも開催して頂ければいつか参加したいです。
・Oさん 50歳 NDロードスター
先日のオーバルレースではお世話になりました。
1日中、自分的にはかなりの距離を走ることができ、昔に比べてクルマを制御するレベルは格段に上がったのではと認識しています。やはり、たくさん走れるのがユイレーシングスクールおよびレースの良い点かと思います。同じ動作の繰り返しで単調な部分はありますが、自身のスキルが低いこともあり、毎周違う状況が出てくるのでそれを克服し再現性を高める意識が出てくること、1周毎に失敗・トライと修正・改善を短時間のうちに繰り返しできること、クルマの限界部分の思わぬ挙動を余裕をもって対処しスキルが習得できること、がオーバルのメリットかと考えます。
一方で、こちらから取りにいかなければいけない部分かもしれませんが、自分が客観的に見てどのくらいのポジション・スキルにいるのかが可視化できればいいなとも思いました。参加しているクルマは同じ車種でも中身はそれぞれで、どのくらいが自分のベンチマーク・ターゲットなのかが容易に意識できるといいなとも感じました。
それから個人的な悩みですが、このままノーマルで走り続けるのがいいのか、少しはクルマに手を入れたほうがいのかよくわからないところです。自分の運転スキルを上げていくことが目的なので、経済的にあまり余裕が無い中、いじることより走ることにお金をかけた方がいいと思っていること、クルマをいじると自分のレベルアップなのかクルマのレベルアップなのかわからなくなること、からしばらくはノーマルのままで走っていこうと考えていますが、それでいいのかどうか正直よくわからないところです。
7月のレースもできれば参加したいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
7月のYRSオーバルレースもキャンペーン中です。YRSオーバルスクールを受講したことのある方はぜひ遊びに来て下さい。