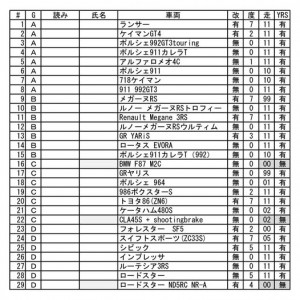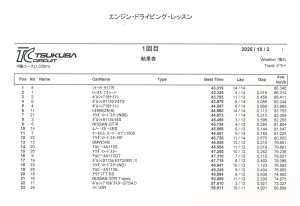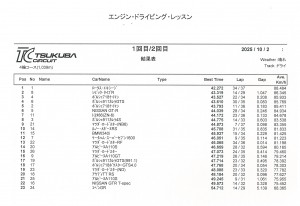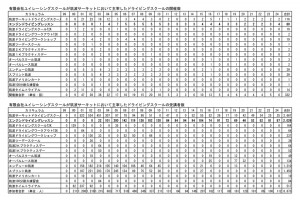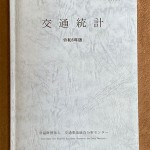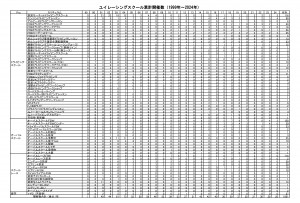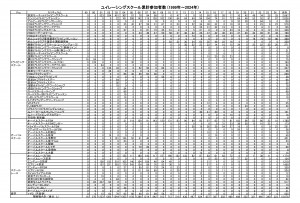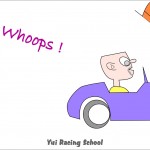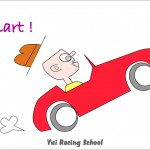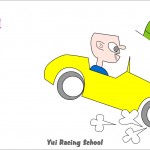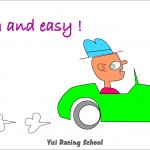第874回 輪荷重
エンジンドライビングレッスンにはコペンGR MTで何度も参加されているAさん。先日のYRSツーデースクールFSWにAさん秘蔵のケーターハム480Sでユイレーシングスクール初参加。240馬力/525Kg、2.19kg/ps、パワーステアリング無し、ブレーキアシスト無しの速く走るためだけに作られたクルマ。シリーズ最速のクルマ。運転を楽しむためだけに所有しているというから羨ましい。
YRSツーデースクールFSWの1日目午前中は、スラロームとビッグブレーキとスモールブレーキの練習。AさんはYRSのカリキュラム初体験だから説明を兼ねてというのもあるけど、個人的に大いに興味をそそられたので1日目のデモランで乗せてもらった。
 重ステと格闘しながらのデモランで前輪の動きがよくわかったと評判に
重ステと格闘しながらのデモランで前輪の動きがよくわかったと評判に
スラロームは重ステと格闘するも、姿勢変化をほとんどしない割りにしっかり荷重移動を感じられる前ダブルウィッシュボーン後ドディオンアクスルのサスペンションに助けられて悪い例と良い例の差を見せることができた。
切り替えしを連続させて逆ロールを起こさせるとロードホールディングが低下する。結果、速く走ろうとするとパイロンから遠ざかってしまう。忙しいけれどパイロンを回り込みながら直線的にスロットルオン➜スロットルオフ➜前荷重の状態でステアリングを回し➜ステアリングを戻して加速➜加速をやめて➜ターンインを繰り返すのが秘訣。
3速全開100キロからのビッグブレーキ。これも悪い例と良い例を目撃してもらうのが目的だけど、ここで望外の挙動を参加者の方にお見せすることができた。その時の画像がないのが残念だけど、想像しながら読んでほしい。
輪荷重という言葉がある。クルマは4本のタイヤで車重を支えている。1本のタイヤにかかる荷重のことを輪荷重と言う。走行中に姿勢変化を起こすクルマの重心は常に移動するから4本のタイヤの輪荷重が刻々と変化している。例えば速度を落としつつ旋回しているクルマの輪荷重は4本どれも異なる。当然アウト側前輪の輪荷重が最大だ。走行中のクルマの4本のタイヤのグリップが均一であることはない。荷重の減少はタイヤのグリップに大きくスポイルするから、クルマの性能を発揮させるためには輪荷重を小さくはしたくない。
3速全開からブレーキペダルを蹴飛ばす。重い。ややあって前輪がロックする。煙があがった。左前輪からだけだ。実はロックしているのは左前輪だけだった。同じ制動力が左右前輪に働いているはずなのに、なぜ右前輪はロックしないのか。
答えはFSWの広大な駐車場の路面にある。よく観察しないとわからないけれど、駐車場は微妙に傾斜している。ビッグブレーキの加速区間はほぼ平坦だけど、ブレーキングポイントから先はわずかに下っている。さらに、歩いても気が付かないほどブレーキング区間が左にむかって傾斜している。
そう。ブレーキペダルを蹴飛ばして左右前輪がロックするほどの制動力が発生した直前、左前輪は右前輪に比べて低い位置にあった。自ずと左前輪の接地圧は右前輪のそれより小さかった。すなわち制動力が立ち上がった時点で左前輪の輪荷重が右前輪に比べて小さかった=左前輪のグリップが右前輪のそれより小さかったのと同じだ。だから左前輪だけロックした、ということだ。
ブレーキペダルを蹴飛ばす悪い例を見せた後、トランジッションを多めにとって踏力を漸進的に増やすスレッショルドブレーキングに移る。テイルスクワットもノーズダイブもしないから重心の移動がつかみにくいが、自分の中で重心が追い越していくのを感じてブレーキペダルに力を加え続ける。ブレーキペダルを蹴飛ばした時には左前輪がロックした瞬間に減速Gが減ったのを感じたけれど、今度は踏力を増やすのに比例して減速Gも増加する。制動距離は短くなり、体感的にはマイナス1G近くの減速Gが発生したいた感じだった。後輪の輪荷重を減らさずに前輪の輪荷重を増やし続けた結果だ。
走行中のクルマの姿勢変化に伴う荷重移動。それぞれのタイヤにかかる輪荷重を意識するとクルマの性能を引っ張り出しやすいかも知れない。
※ 参加すれば実りの多いYRSツーデースクールFSW。申請中の日程が承認されれば2026年春の開催は3月28、29日(土日)になるはず。決定次第お知らせしたい。