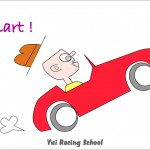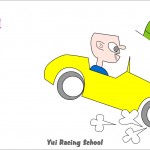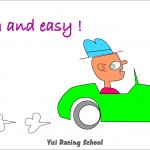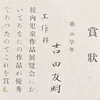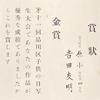第862回 ユイレーシングスクールが考える道具とクルマ
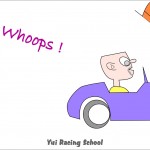
クルマはますます大きくなり続け
どんどん豪華になり速くなり
おせっかいを焼きたがるようになった
しかしクルマはいつの時代も人間の良き相棒だ
相棒だから一生懸命付き合わなければならないと思う
ユイレーシングスクールの主宰者として、個人的にはクルマはかけがえのない相棒だと思っている。何よりも高校1年の春に軽免許をとって全長3m、排気量360ccの自動車を公道で運転した時だった。間違いなく世界が変わったことを気づかされ、さらにクルマは人間に自由と時間を与えてくれる『人間能力拡大器』だ、一生付き合っていくべき対象なんだと確信した。
以来60年。クルマを相棒として尊敬の念を抱き、相棒とどうやってうまく付き合うかを考え続け、サーキットを走ればまだまだ速くなり、76歳になっても運転を楽しんでいる自分に気づき、改めてクルマの存在をいとおしく思っている。
だから、もっともっとクルマを上手に動かしてあげたい、クルマの性能をキッチリと使ってあげたいという思いが強い。
だから、ユイレーシングスクールに来る人達にももっとクルマを好きになってほしいと思う。
だから、クルマさんと付き合ううえで大切なことを話しておきたいと思っています。
世の中には様々な道具がある。包丁のような単純な道具から、高度で複雑な技術で作られたクルマまで、基本的に人間の営みを豊かにするために道具は生まれてきた。ただ、どんな道具にも使い方がある。使い方を間違えれば道具はその機能を発揮することができないばかりか、人間に牙をむくことさえある。
みなさんは包丁でモノを切る時に引いてきりますよね。なぜ引いて切るほうがよく切れるか想像したことがありますか。
刃物の刃は薄いほうがよく切れるのは広く知られています。しかし包丁の耐久性を考えるとある程度の刃の厚さは必要です。そこで薄くはない刃のついた包丁を引くことで、『人為的に』包丁の刃の厚さを薄くしているのです。包丁の刃の厚みが薄くなるわけがないと思う方は、2011年1月にアップした ルノー・ジャポンの公式ブログ「第6回 道具を使う」 を読んでみて下さい。
みなさんは小学校の手洗い場に並んでいる蛇口から水が滴り落ちているのを見たことはありませんか。おおかたは水が落ちてないのに、中には滴り落ちている蛇口がある。そんな光景です。
たくさんの子供が開け閉めする蛇口ですが、子供が蛇口の使い方を知るよしもありません。今はカートリッジタイプの蛇口が増えたので水漏れは少なくなりましたが、パッキンを使っている蛇口は漏水と背中合わせです。ではどうすればパッキン式の蛇口を長持ちさせることができるのでしょうか。これも道具の使い方の一つです。
水を止めるために蛇口を思いっきり閉めるのは間違いです。いったん蛇口を閉めて水を止めるのはかまわないのですが、その時に力が入りすぎてパッキンを必要以上につぶしている可能性があります。パッキンはつぶれることを繰り返しているうちに厚みがなくなり水を完全に止めることができなくなり、結果として水が滴り落ちることになります。正解は、いったん水が止まったら水が蛇口から漏れる寸前までハンドルを戻す、ことです。
意識してハンドルを戻そうとすると手間はかかるかも知れません。ですが、パッキンがつぶれないように閉めるのが正解だと理解していれば、そのうちに必要以上の力で閉めることはしなくなります。
クルマも運転も同じです。道具としての包丁や蛇口とクルマには大きな開きがありますが、使い方を間違わなければきちんと機能してくれる道具です。ユイレーシングスクールは道具の使い方としての操作を理論的かつ合理的に理解してもらい、それらをたたき台に反復練習できる機会を設けています。全ては道具としての相棒であるクルマさんに気持ち良く走ってもらうためです。
みなさんもぜひユイレーシングスクールに遊びに来て下さい。真剣に遊ぶ方法をお教えします。