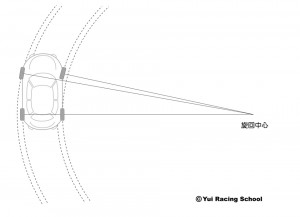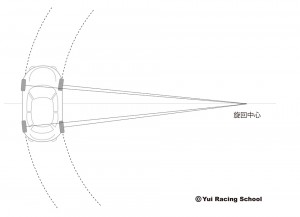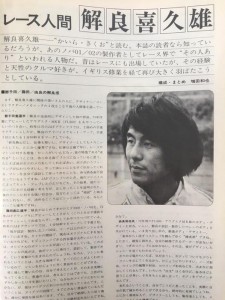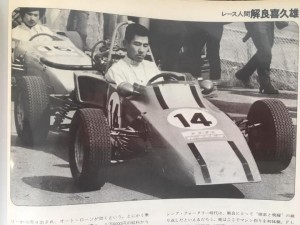第854回 OさんとIさん@YRSツーデースクールFSW
少しばかり?前のことなのだけれど。

3月22日
朝6時16分
御殿場市山の尻から富士山を仰ぐ
2025年春のYRSツーデースクールFSW1日目

ウルティムに乗るIさんが
4コントロールを駆使して
スラロームを駆け抜ける

Iさんと3台目のメガーヌRS
メガーヌⅢRSシャーシカップから
メガーヌⅢRSトロフィーRへ
そしていつの間にかメガーヌRSウルティムに

YRSツーデースクールFSWの特長はとにかくたくさん走ること
加えてミーティング=アドバイスの多さ
1日目午前中は広大な駐車場で
スラローム走行とブレーキング練習2種類
午後はオーバルコースを走りっぱなし

YRSツーデースクールFSWの2日目は
ショートコースのコース歩行から
走行上の注意点を自分の足で確認
朝が早いので影も長く

初めてユイレーシングスクールに参加する方と
初めてサーキットを走る方を優先に
リードフォローで1周のリズムをビルドアップ
リードフォローに次いで同乗走行
その後3グループに分けて短いセッションを繰り返し
午前1回午後2回の計測を

この日はメガーヌRSウルティムの試乗会を併催
2台のウルティムを用意して
スクール参加者にウルティムの走りを味わってもらった

ウルティムが1コーナーをクリアし
2コーナーから8%登りのヘヤピンを抜ける

試乗を終えたスクール参加者は
口々にウルティムに乗った感想を

2日間のスクールが終わり帰途へ
3月23日
午後5時31分
FSWから富士山を仰ぐ
富士山の頂きにひと筋の飛行機雲が

YRSツーデースクールFSW前の燃料補給
今回は御殿場ICにほど近い大和田さんへ
ユイレーシングスクールはサーキットを走行するカリキュラムでは周を重ねるごとにラップタイムを短縮するような走り方の構築を勧めています。いきあたりばったりの運転やall or nothingの走り方では操作が身体に馴染まないからです。計測周の最後にベストラップが出るのが理想と伝えます。もちろんそのために途中のアドバイスも欠かしません。
今回ユイレーシングスクールに参加するのが初めてで、サーキットを走ったことのないIさんが、その教えを具現化してくれました。Iさんは午前中に計64周、午後1回目に計44周、午後2回目に計48周と計測周だけで156周、全参加者のうちで最もたくさん周回しました。しかもベストラップを午後2回目の48周目、つまりこの日走った156周目にたたき出したのです。スクールをやっていてこれほど嬉しいことはありません。Iさんが乗っているクルマの絶対的な速さから見ればあと1秒強縮めることが理想ですが、Iさんなら間違いなくできるはずです。
YRSツーデースクールFSWは運転操作が自然に身につくようにカリキュラムを組んでいます。サーキットを走ったことのない方もサーキット走行のベテランにも有効な内容です。
ユイレーシングスクールではYRSツーデースクールFSWを年2回開催していますが、今年2回目の秋の日程が決まりました。11月1、2日の土日に開催します。参加申し込み受け付けは9月初旬を予定しています。運転で次のレベルへと考えられている方は、ぜひ参加を検討してみて下さい。