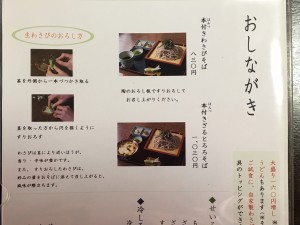第231回 今年もやるそうです
ルノーネクストワン徳島とルノー松山が、ルノーユーザを対象に安全に運転を楽しんでもらうために20年も開催し続けているルノークラブ走行会。今年もゴールデンウィーク最中の5月3日に四国の阿讃サーキットで開催されます。
走行は午後1時から。午前中は『理にかなった運転操作』をテーマに座学を行います。
中国四国地方にお住まいのルノーユーザで「制限速度なしのサーキット」を走ってみたい、クルマの動かし方の理論を聞いてみたいはユイレーシングスクールまで連絡して下さい。ルノーネクストワン徳島の一宮さんに取り次ぎます。もちろんボクも行きます。一緒に運転を楽しみたいと思います
◎ 阿讃サーキットはこんなところ
◎ ルノークラブ走行会について過去の記事
第230回 エンジンドライビングレッスンと焼き蛤
クルマを存分に味わいつくすことを目標に掲げる雑誌エンジン+ユイレーシングスクールのドライビングレッスン。あしかけ14年間で58回開催。
ユーザーの所有欲を使用欲に転換することに十分貢献していると自負している。

クルマの性能を引き出すコツがわかれば運転が楽しくなる
アドバイスを聞く参加者の顔はみな真剣

今回、14年目にして初めて参加者が20名を切ったのが残念
それでも走り終えた後はみんな笑顔、笑顔
※5月11日(木)。富士スピードウエイで午前中にオーバル練習、午後にショートコースを走るというエンジンドライビングレッスン初めての試みを行います。興味のある方はエンジンドライビングレッスンオンラインの頁で会員登録をして詳細をご覧下さい。参加募集開始は11日(火)からです。
※会員登録しても参加する義務は生じません。
ところで、
大津市に住居を構えるまでは千葉県の八千代市に本拠を置いていた。千葉県と言えば海があって海産物が大好物なボクにとっては天国。時間ができるとあちこちに出かけていったものだ。
で、今回筑波サーキットでエンジンドライビングレッスンがあるのだからと、ちょっと足を伸ばして鹿島経由で行くことにした。
目的はホントに久しぶりの地の蛤。カシマサッカースタジアムの先にあるやましょうさんにお邪魔した。
また行くぞ ! ! !
※写真の撮影許可はもらいましたが、やましょうさんから何かしていただいたということは一切ありませんので。
第229回 他にやることあるだろうに
年度末が近くなるとそこかしこで道路工事が始まるのは世の常。いろいろと事情があってのことだろうけど、道路の補修や改良ならまだしも、中には目的が理解できないというか、必要性が感じられない工事がある。

工事はけっこう大がかりなものだった
大物地区への側道から見た工事現場
国道161号線から湖西道路への接続道路。左折すれば湖西道路の京都方面、湖西道路をくぐって、すぐに右折すれば湖西道路の高島方面、くぐってから最も奥の車線を右折すると大物地区への側道、という交差点がある。
そのそれぞれの車線を行き先ごとに色分けする工事が行われていた。結果、京都方面が赤っぽく、高島方面が灰色っぽく、湖西道路を志賀インターチェンジで降りて161号に向かう車線が黄色っぽくオーバーレイされた。

直進するとこんな景色
一万歩ゆずって色分けを認めるとして
赤色と灰色がこんな風に分断されているのはおかしなデザインだ

やるならば赤色と灰色半分ずつで車線を塗り分け
それぞれの方向に収束させるべきだろう

湖西道路をくぐってから振り返った景色
湖西道路を志賀インターチェンジで降りてきたクルマが
一旦停止の標識があるにも関わらず止まることもなく
黄色の車線からはみ出して走っているし
決してきれいな色分けとは言えないし
なんだかなぁ

高島方面に向かう湖西道路を志賀インターチェンジで降りると広がる景色
何日もかけ、かなりの人数がかかわった工事だから相当なコストがかかっているのだろう。しかしこの工事の結果、誰が恩恵を受けるのだろうかと考えると、実はクルマを運転している我々ではないようだ。色分けされてなくてもそれぞれの方向に誘導する標識は以前から完備していたから。
いろいろな事情があって工事をするなら、意味のない色分けをするより、夜中になると真っ暗になる湖西道路の路側帯との境にキャッツアイを埋め込むとか、道路を使う人の立場に立ってコストをかけるべきなのではないか。
運転を安易にする方向の工事は必要だと思わない。運転するには、注意力を維持したり集中力を保つためにある程度の努力が必要だ。人に楽して運転してもらうのが行政の役目だと思っているなら危ういものがある。
人々が安心して運転に集中できる環境作り、合理的な交通環境の整備にのみコストをかけるべきだ。そうでないとなんのための道路行政かわからなくなる。
写真が見つからないのだが、以前あった話。
湖西道路の路肩にある電話で落下物を通報しようとして扉を開けたら、「現在故障しています」の張り紙。何かあったらどうするのだろう。携帯電話があるから使えなくても問題ない、との判断で放置していたとは思いたくないが。管轄は違うかも知れないが、我々にとっては同じ交通のインフラだ。
交通環境にはやるべきことがたくさんある。色分けのコストも源流をたどれば我々の税金のはず。やったつもりにならず、道路を使う人が「さすが!」と感心するようなコストのかけかたをしてもらいたいものだ。
第228回 Yui Racing School の2
ユイレーシングスクールのYRSオーバルスクールでどんなことを教えているか、その一部が WEB|CARTOP に動画で紹介されています。ご覧下さい。
※ 他のカリキュラムでも、いかにしてクルマの性能を発揮させるかに焦点をあてたアドバイスをしています。ルノーユーザーの方はぜひ遊びに来てみて下さい。カングーも大歓迎です。
第227回 ダブルニッケルが懐かしい
ロサンゼルス空港の周回路の出口で右折してパシフィックコーストハイウエイに合流。滑走路の下をくぐり105Eastに乗って東へ向かう。105フリーウエイはパシフィックコーストハイウエイの西で一般道に変わるのでそれほど交通量は多くない。4車線にクルマが点在する。
しばらく進みオレンジカウンティ方面に向かうため405Southに向かう。いくつかの合流を経て5車線プラスカープールズレーンの405に乗る。とたんに交通量が増える。頻繁な車線変更あり。
405フリーウエイはアメリカ西海岸をメキシコとカナダを結ぶ大動脈のインターステイツ5号線の「海寄りバイパス」のようなものだから、1日中交通量が多い。
405に乗ってスピードメーターを見ると80mphあたりを指している。俗にグレーターロサンゼルスと呼ばれる広大なエリアの制限速度は65mphなのだけれど、間違いなく405を走る全員が制限速度を守っていない。
だからけしからん、という話ではなくて、都市部のフリーウエイの流れが速くなったから、効率的にクルマを使えて便利になったという話。実際、空港を出てからファンテンバレー市の自宅までの所要時間は昔に比べて20%近く短縮した。
1979年にアメリカに居を移し、サンタモニカやレドンドビーチなどを転々としてファンテンバレーに落ち着いたのだけど、ずっとフリーウエイの制限速度と言えば55mphだった。信号や一旦停止がないからフリーウエイなのに、なん車線もある広い道なのにとダブルニッケルを恨んだものだ。

昔に比べて速度制限の標識の数が減ったように感じた
65mphが周知の事実だからか
他に理由があるのか
制限速度を無視してはいけないが事故を起こさないことのほうが最優先されるべき、と考える者にとって、制限速度を守れば安全を担保できると考える人々は苦手だ。その昔。朝夕のラッシュ時にフリーウエイに乗ると「私は安全運転しています」と言いたげな、流れの速さに竿をさすようにマイペースで走るご仁に出会うことが少なくなかった。そういう人々が渋滞の元凶なのはいうまでもない。
さて、1973年のオイルショックの時にガソリンの節約を目的に連邦法で55mphと定められた制限速度だが、クルマの性能が良くなり燃費が向上し、道路のインフラも充実してきたからなのだろう、1995年にフリーウエイの制限速度が各州がそれぞれに州法で決められるようになった。
グレーターロサンゼルスはこの年から都市部の制限速度が65mphに引き上げられた。当時、速度を上げると危ないとか否定的なニュースも耳にしたけど、間違いなく交通の流れはスムースになった。事故件数が増加したという報道を目にしたこともなかった。
結局、安全運転信奉者も65mphで走ることになったので流れの速さが底上げされて、それでフリーウエイの流れに淀みがなくなったのではないかと想像している。
それにしても、80mphは行き過ぎじゃぁとも思うけど、流れに乗って走っていれば速度違反は咎められないことは経験的に知っているし、とにかく周囲から浮いた運転をしないように自宅を目指した。
個人的には制限速度はもっと速くていいと思うけど、速く設定するとまたそれを上回って走る人がでてきくるから、どこで線を引くか難しいところ。アメリカのフリーウエイは路面の悪い所があるからむやみに速度を上げるのも危ない。実質80mphならよしとしましょう。

《訂正》 第226回でカープールズレーンを1人で走った場合の罰金の金額がわかりました。現在は341ドルです。80年代は確か100ドルぐらいだった気がするので、罰金も値上がりしているようです、
【余談1】 州法で制限速度が決められることになって、モンタナ州は制限速度そのものを撤廃してしまった。結果、全米の走り屋がモンタナ州を目指したとか。ところが事故が相次ぎ結果的に規制することになったと聞いた。
【余談2】 ご存知かも知れませんが、ダブルニッケルのニッケルは5セント硬貨の俗称で制限速度が低いことを揶揄した造語です。
第226回 カープール?
盲目的にアメリカが好きなわけではないけれど、ことクルマを使う上ではアメリカを高く評価しないわけにはいかない。
それはモータースポーツの話だけではない。
例えばカープールズレーン。アメリカに住み始めた70年代後半にサンタモニカフリーウエイで初めて経験したのだが、1台のクルマに2人以上乗っている場合にのみ通行できる車線のことだ。
4車線であれば第4車線がそれにあたり、追い越し禁止の黄色いラインとはみ出し禁止の白い実践で区分けされている。
いうまでもなく1台のクルマに2人以上乗ることを奨励し、結果としてフリーウエイを走るクルマの総量を抑制し、最終的に渋滞の減少を図ろうというもの。

頻繁に目にする標識
1人乗りで走ると、確か250ドルぐらいの罰金
これも当初に比べると値上がりした
昼間カープールズレーンを走っているクルマはそれほど多くはないけれど、朝のラッシュ時にはカープールズレーンでも渋滞が起きるほど活用されている。

アメリカの道は交通の流れに淀みがない
淀みを作らないような工夫がいい
それは単に土地が広いからだけではない
当初、通勤時間の短縮になるとはいうものの、ライドシェア=乗り合いに慣れていないアメリカ人はあまり利用しなかった。が、通勤圏が拡大しロサンゼルス中央部への流入車両が増え通勤に時間がかかるようになると、合理的なアメリカ人はほっておかなかった。
いまだにロサンゼルス近郊はフリーウエイの拡充が進められていて、カープールズレーンが2車線あるところとか、3人以上乗っている場合に走れるレーンなんてのもがあったり、カープールズしか通れないジャンクションのオーバーブリッジがあったりする。

その昔カープールズレーンを合法的(?)に走るために
助手席に乗せる空気で膨らませる人形が売っていたのを思い出した (笑)
とにかくアメリカのクルマ社会は合理性に富んでいる。道の作り方だけではなくルールにしても、どうすればクルマを効率的に使えるかを常に誰かが考えていて実行し続けている感じがする。だからアメリカの道を走る時にはストレスを感じない。

久しぶりのアメリカ初日はやはり、ハラペーニョいっぱいのピザにした。
◎
第225回 郷に入っては郷に従え
名古屋で生まれて初めての体験をした。
右折車線のある交差点の通過方法が、16歳で免許を取ってから一度も経験したことのないものだった。

片側3車線の出来町通りを西に進んでいて第3車線の色が違うことには気づいたのだけど・・・

先を急ぎながら第2車線を進んでいると路面に描いてある進行方向を示す矢印が妙な具合に・・・

なんと第2車線を走っていた先行車が信号の手前で止まっている !!!
第2車線を走っていたから続いて止まったけれど・・・
片側3車線道路の第2車線で止まることがあるなんて想像したこともなく・・・
矢印式の信号は直進のみ点灯だからその場から動けず・・・

第2車線で止まっているクルマの両側を直進するクルマがかなりの速度で直進車がすり抜けて行く
たぶんスズキもスバルも制限速度を超えている
だって止まっているクルマが揺れるもの (笑)

面白いからグルッと回って別の交差点で再度挑戦
右のマツダも左の軽バンもかなりスピードを出している
おまけに第3車線の先はシケイン状になっている(!)から迫力満点
結局、色の異なる第3車線はバスレーンで、バスレーンが第1車線にないことに起因するシステムのようだ。
郷に入っては郷に従え、ってことなんだろうけど、知らないと戸惑うね。
第224回 Yui Racing School
ユイレーシングスクールが主催するYRSオーバルスクールがWEB|CARTOPの取材を受けました。既に掲載されています。ご覧下さい。