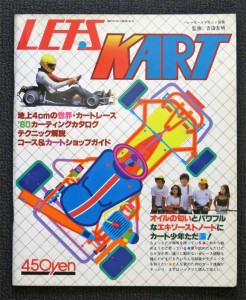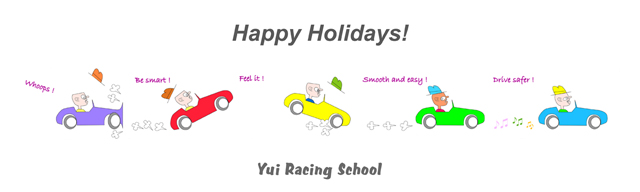第767回 Wさんの場合

ユイレーシングスクール初参加は
2017年3月のYRSツーデースクールFSW
それ以来
いつもご夫婦で来てくれるWさん
ご主人は顔出しNGだから例によって
ルノー乗りになったWさんには早速感想文を
昨年12月に中古でトゥインゴGTを購入しました。
実はトゥインゴGTにはかなり前から興味があり、中古車サイトをいろいろと物色していたのですがなかなかいい出会いに恵まれていませんでした。11月にルノー沼津の三島アプルーブドカーセンターで認定中古車が出てきて妻と二人で実車を確認して、1日悩んで購入を決意しました。オプションがてんこ盛りで購入後もほとんど手を入れる必要が無さそうだったのと、前のオーナーが大事に扱っていたことが感じられたのが購入の決め手でした。(ディーラーの担当者も非常に良い方でした。)
トゥインゴGTに興味を持った理由は、以下となります。
・5ナンバーサイズでコンパクトなこと
・RRレイアウトという駆動方式
・ルノースポールによるチューニング
・MT車が選べる
・フランス車(ルノー車)ってどんな乗り味なんだろう?
ある意味、今後二度と出てこない変態車に心引かれてしまいました(笑)
現在の愛車はトゥインゴGT以外に下記の2台に乗っています。
・718ケイマン
・NCロードスター
後輪駆動のMT車という共通点以外はレイアウトも車の乗り味も全く違う3台となります。
乗り比べると
718ケイマン
・非常にソリッドで、ステアリングからのインフォメーションもわかりやすい。
・足回りは堅いが、しなやかさも持っている。
・自身の直後にあるエンジンからの振動、音もその気にさせる。
・シフトレバーも節度やコクっとしたフィーリングで気持ち良い。
・ブレーキのタッチ、効き、耐フェード性はこれまで乗った車の中で最高。
・意外と低速トルクが無いため、他の車であれば2速でいけるところが1速まで落とさないと前に進まない。
・雨の日の挙動(スクール参加時やサーキット走行時)は正直怖い。電子制御を入れてもスピンしやすい。
NCロードスター
・車体は緩いが、挙動はわかりやすい。
・軽量な車体とエンジンパワーのバランスが取れている。
・MTでもイージーなドライブができる。
・オープンドライブは一度味わうとやみつきになる。
・雨の日に電子制御を切っても安心して操作できる挙動(スクール参加時やサーキット走行時)。
購入後は町乗りメインで使っていたので、トゥインゴGTの実力を知るためにオーバルスクールに参加させて頂きました。
スクールで自分の腕なりに車を操作して反応を確認し、以下の感想を持ちました。
・挙動はかなりクイック(前が軽い事と、ホイールベースが短いためだと思います)。
・目線は高いがコーナリング中に車が転倒するような気配は感じなかった(当たり前ですが)。
・パワーは無いですが、後ろが重く、後ろから押される感覚は新鮮。
・絶対的なスピードが遅いため、私のような未熟者でも手の内感を持って操作ができる。
・シフトレバーの感触が緩い、横Gがかかっているとシフトが入りづらい事がある。
・ブレーキのタッチがこれまで乗ったどの車とも違う(遊びのストロークが長い)ため違和感があったが、連続して乗ることが感覚は掴めた。効きに関しては問題ない。
小さい車をMTで操って乗るのは、もの凄く楽しい事を再確認しました。以前乗っていたマーチ12SRを思い出しました。
これまでの愛車歴
マーチ12SR
ランサーエボリューションX
BRZ
ゴルフGTIクラブスポーツトラックエディション → YRSに参加し始めた
E90 M3セダン
F87 M2クーペ
NCロードスター
718ケイマン
トゥインゴGT
以上です。