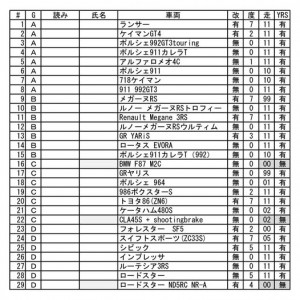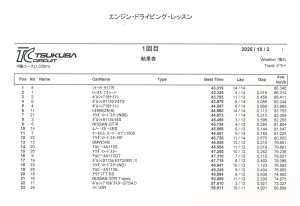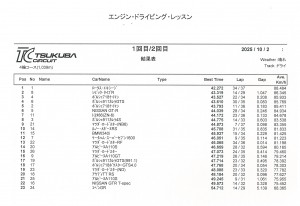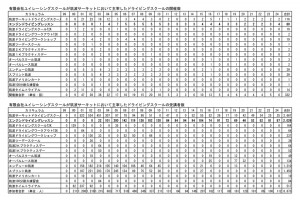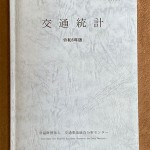第877回 引っ越し
2010年11月17日の第1回からまる15年。870余回。月平均4.9回の更新を誇るルノー・ジャポン公式ブログのトム ヨシダブログ。
ルノー・ジャポンの広報から好きなことを書いて構いませんと言われ、気の向くままに好きなクルマのこと、好きな運転のこと、好きな食べ物のことなど書き散らかしてきました。
長期にわたりお借りしたルノーの歴代RSモデルをとことん味わいつくし、スクールカーとして参加者に体験してもらうこともできました。このブログを読んでRSモデルを購入した方は新車中古車合わせて20名を下りません。ボクが終の相棒に選んだルーテシア3RSが生き生きと走る様を見るのは幸せでした。ルーテシア3RS、ルーテシア4RS、メガーヌ3RS、メガーヌ4RS、トロフィーR。購入された方がユイレーシングスクールに足を運んでくださったのは望外の喜びでした。
※12月6日のポルシェクラブ東京銀座ドライビングレッスンにメガーヌRSで参加した武松さん。会うなり「真似しちゃいました!」。嬉しいじゃないですか。
元はと言えばルーテシア3RSにひと目惚れしたのがきっかけで始まったこのブログですが、このたびルノー・ジャポンがブログがのっている古いプラットフォームを更新しないことを決めました。なのでこの第877回をルノー・ジャポンの公式ブログとしての最終回としてひと区切りつけることにしました。
しかしながら15年870余回というのは簡単に括れるモノではありません。ブログに登場した方々の思いが込められています。ボクが主宰するユイレーシングスクールの主張も願いも込められています。クルマ、運転、食べ物、季節。とにかく守備範囲の広いブログに育ちました。書いてきた自分自身も将来読み返してみたいと思うはずです。なのでルノー・ジャポンの公式ブログの内容をそのままユイレーシングスクールのブログに移転して、これからもトムヨシダのブログとして書き続けることにしました。
・ ユイレーシングスクールのブログに名前を変えたトムヨシダのブログはこちらでお読みになれます。
また現在ユイレーシングスクールのWebサイトの見直しも行っています。年内にはお披露目できるはずです。これからもユイレーシングスクールとトムヨシダのブログをよろしくお願いします。
※ プラットフォームが存続する限りはルノー・ジャポンの公式ブログでもお読みになれます。