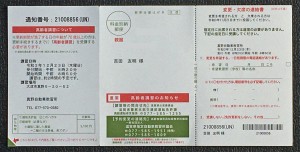※ 先日のYRSオーバルスクールFSWには2人のOさんが参加。なので 第619回 で感想文を紹介したOさんをOKDさん、今回登場してもらうOさんをOKBさんとすることにしました。

スマホでラップタイム計測
フライングラップに入るOKBさんとルーテシアⅢRS
このブログにたびたび 登場してもらっているOKBさん
OKBさんにも感想文をお願いしておいた
ガールフレンドの感想文と一緒に届いたのでここに紹介
【OKBさんの感想文】
ちょうど1年振りの受講で、通算8回目の走行です。スクールの進行と雰囲気にも慣れ、車両もばっちり整備したのでリラックスして走ることができました。今回、強く感じたのはメンタルの大切さです。落ち着いた状態だと車の挙動もよく感じ取れるし、操作のタイミング・緩急を周回ごとに変えて試す余裕も生まれました。コース幅だって今までより広く感じられ、多少のミスはかまうものかと思えたほどです。それは講師陣にも伝わったようで「車を積極的に動かそうとしているのが遠くからでもわかる」と嬉しいコメントも。それと、視線で走りが変わることも実感しました。これは先に感想文を寄せているOKDさんからのアドバイスでもあったのですが、コーナー入口の時点で出口側を見ながら操作すると、とてもきれいに曲がれるのです。こういったひとつひとつの行動や操作が積み重なって、速さにつながっていくのですね。次はこうしよう、ああしようと走るうちにあっという間に終了時間になりました。振り返ると「こうすれば良かった」という、後ろ向きな気持ちを一度も感じない一日でした。次回の受講では「待つ」操作を模索してみるつもりです。
ところで、今回は彼女にも同伴してもらっていて、目的はトムさんの同乗走行の体験でした。はじめに私が運転する同乗走行を体験、次にトムさんの同乗走行へ。私の狙いとその結果は?彼女の感想文へ続きます。

ルノー仲間のOKDさんとOKBさん
OKDさんはユイレーシングスクール初参加
以前ルーテシアZENで参加していたOKBさんは8回目
ルノー談義に花が咲く
【OKBさんのガールフレンドの感想文】
OKBさんの付き添いとして参加させてもらいました。日常の運転技術向上を目的に彼がスクールに初めて通ったのが約3年前です。その時に、上手な運転とはどういうものなのかを実感したようで、嬉々として帰ってきたのを覚えています。その後も、日々の運転を見直すために、緩やかなスパンでレッスンに参加していたようです。
そんな彼から、助手席に乗ることが多い私に「一度トム先生の上手な運転を体験してもらって、自分の運転との違いを客観的に教えて欲しい。」と言われました。近所を運転する程度の私が、車のことについて分かるものなのかと思いながらも、何か役に立てればと参加した次第です。
午前中は座学と実技でした。2台ずつ小さめのコースを周回し、各車両の運転手に無線ラジオで走行について指導がありました。3回目くらいに彼の運転に同乗しましたが、通常よりもスピードが出ている車体に機敏なハンドル操作が求められる走行で、正直「怖いなあ。」と思いました。その後、トム先生に運転を交代、助手席に同乗させてもらいました(彼は後部座席へ)。彼の走行よりも速度が出ているのに、車体がぶれていないからか怖さを感じませんでした。車本来の性能を引き出す運転とはこういうことなのかな…と素人なりに感じました。
午後はコースをさらに大きくし、距離を伸ばして練習しました。参加者全員で直列になったり、2台3列で並走したりとレベルの高い練習もしていたようです。
参加していた方々は、当然のことながら車が大好きという印象で、車について教えてもらったり情報交換したりする場としてもとても良い機会だろうなと感じました。
余談ですが、運転を見る以上に、同行されていたご家族の方と楽しくお話させていただく時間のほうが長かったです(笑)車好きの旦那さんの影響で、お二人の奥様もかなり詳しくて、趣味に理解があって、とても素敵だなと思いました。参加させていただき、ありがとうございました。

OKBさんとガールフレンド
また遊びに来て下さい

旦那さんとボーイフレンドに交じって
デモランの説明を聞く
真剣に
メガーヌRSのオーナーのOKDさんは助手席
左端はNCロードスターを増車した
BMW M2オーナーの常連Uさんご夫妻

旦那さんとボーイフレンドは走りに夢中
奥さんとガールフレンドはおしゃべりに夢中の図

ユイレーシングスクールに初参加のOKDさんが
YRSオーバルFSWロンガーの下のコーナーに飛び込む
OKDさんに感想を書いてほしいとお願いしておいたら早速に
一緒に来られた奥さんからの感想文も(喜)
【OKDさんからの感想文】
11月6日のオーバルスクールに参加させていただきましたOKDです。レーシングカートを24年ほど続けており、数年前よりKZクラスと云う”シフター”クラスにステップアップしました。このクラスはヨーロッパで主流の125CC+ハイグリップタイヤのミッションカートカテゴリーで、繊細さと、思い切りの良いドライビングの両方を求められます。
元々、小さいカートコースでカートを始めた事と、学生時代にジムカーナを少し齧ったこともあり、ステアリングの切り方がコーナーの奥まで入って、パキっときる癖があるのと減速時にスピードを殺し過ぎる癖を矯正したくスクールに参加しました。
元々、感覚派の運転手なんですが、理論的な説明と同乗走行で今迄、こうあるべき、と思っていたことが崩れて行き、あ~、思い違いをしていたなぁと思うことが多々ありました。(特にトレールブレーキ) 悔しいのは、その理論に自分の染みついた癖をアジャスト仕切れず、最後まで納得の行く走りが出来なかったこと。半面、面白いのはスクールの翌日から、荷重の振り分けとか、今まで考えてなかった事を考えながらクルマを走らせるようになったことでしょうか。
今シーズンのスクールは終了と云うことなので、また来年参加したいと思っております。とりあえず、12月初旬に岐阜の瑞浪でカートレースがありますので、今回の経験を少しでも生かして走ってきます。
最後に、私、現在54歳ですが、ドライビングに対する探究心、向上心が有る限り、伸びしろはあると実感しました。年齢に関係なく、ドライビングスキルを上げたい、見直したいと思う方にはお勧めできるスクールです。
トムさん、今回は有難うございました。また、次回、お会いできる日を楽しみにしております。
【一緒に来られた奥さんからの感想文】
私は主人の付き添いで見学をさせて頂きました。車の運転が上手いとはどういうことか、を座学と実践で体験できるスクールだと思いました。初めに講義では分かりやすいグラフや図を使って理論を学びました。それから主人は実際に車を運転し、その間、トムさんやスタッフの方から、オンタイムで無線による指導を受けていました。私はトムさんの運転する車にも乗せて頂きましたが、コーナーを曲がる際も滑らかな走りで同じ車でも乗り心地が違った感じでした。主人もこれからは学んだことを活かして車に優しい快適な運転をしてくれることと思います。
今回、スクール会場では、他にも付き添いの方が何人かいらっしゃって、その方々と待ち時間もおしゃべりしながら楽しく過ごすことができました。久しぶりの外出先で、トムさんもスタッフの皆さんもとてもフレンドリーで、景色の良い中、リラックスもでき良い一日となりました。また次の機会を楽しみにしています。

OKDさんご夫妻
また遊びに来て下さいね。

11月5日朝6時14分
前回掲載した写真を撮ってから移動
山の尻から新御殿場ICに抜ける
新たに作られた道を探索
遠くに建設中の新東名が見える

11月5日朝8時40分
沼津港へ移動し
いつものむすび屋さんでまずは地アジ刺し
そろそろアジの旬も終わりか

同
この日のメインは
本マグロ中トロ鉄火丼

同
この日の中トロはとびきり

11月6日朝5時59分
東の空が赤みを帯び始めるも
富士山は雲隠れ

11月6日朝6時12分
クルマの中で待っていると
待望の富士山が

11月6日午前8時50分
YRSオーバルスクールFSW
教室での座学を終えて
ユイレーシングスクール初参加のOさんに
クルマを借りてデモラン

11月6日午後6時15分
この日は寒かったり暑かったり
何度ダウンジャケットとダウンベストを
脱ぎ着したことか
身体を温めるために須走の長楽へ
昔ながらのラーメンがウ・マ・イ

11月7日朝5時57分
須走の扇屋さんの屋上から
富士山を仰ぐも雲の中

11月7日朝6時57分
FSW駐車場から
御殿場市の上にただよう雲海を見下ろす
まるでホントの波のように

11月7日朝8時53分
今年4回目の
ポルシェクラブ東京銀座ドライビングレッスン
座学を終えて富士山が雲に隠れる前に
記念撮影

11月7日午後4時46分
片づけを終えて
西に向かう前に
最後の一枚

5日。朝6時8分の富士山を御殿場市山の尻から仰ぐ
この直後に紅い富士山が
それにしてもずいぶんと日の出が遅くなった

2006年に始めたYRSツーデースクールFSW。多くの方がここからサーキットデビューを果たしました。その通算29回目はまんま運転日和。2日目のショートコースは23名が走行で昼休みの記念撮影。

顔を見せたいということで
一瞬だけマスクを外ししゃべらないで記念撮影
OKが出たところでマスクをつけるの図

今回はユイレーシングスクールとサーキット走行初体験の方が3名とサーキット走行が1時間以内の方が2名が、ユイレーシングスクールに20年通っているベテランに交じってスキルアップ。23名が午後の計測ラップだけで1周867mのコースを合計1,663周。今回はスピン1回、ハーフスピン1回を目にしてしまったのが悔やまれる。

10月28日木曜日
今年2回目のYRS+エンジンドライビングレッスンが終わった
2003年に第1回を開催してから71回目だった
「所有欲から使用欲への転換」をテーマにした大人の運転学校は
来年20年目を迎える
秋晴れの下、今年2回目のYRSツーデースクールFSWを開催。21歳から74歳まで平均年齢50.7歳の運転好き24名が2日間、休む暇もなくこれでもかと言うほど走りこみ。今回は好天に恵まれ参加された方々にとって充実した2日間だったはず。でも秋ですね。日が陰ると急に寒くなるようになりました。

この日のルノー仲間
前列左から埼玉県からのSさん、ワタクシ、三重県からのWさん
後列左から三重県からスタッフのY、千葉県からKさん、神奈川県からのYさん
ツーデースクール常連の四国は香川のIさんから前々日に電話
仕事が終わらず参加不可なので来年はと
まだ日程は確定していませんが来年3月に申請はしてあります
1回で10回分の進歩が期待できるYRSツーデースクール
みなさんの参加をお待ちしています。
3種類あるカメラの画角を最も狭い135度にして、気分的には追突しそうになるくらい近づいたけれど何事もなかったような映像に。これは新発見。機会があればどこまでアップにできるか試してみよう。
今年のYRSオーバルスクールFSWはあと2回。11月6日(土)と12月19日(日)。運転の概念が変わります。クルマとの対話が進みます。コーナリングが間違いなく楽しくなります。ぜひ参加してみて下さい。詳しくは YRSオーバルスクールFSW開催案内 をご覧下さい。

動画の撮影はこんなふうに
第606回で触れたクラッチ交換と同時にトランスミッションのマウントを交換したスタッフY。ワタクシの終の相棒も同じモデルだから参考になると思い、交換にいたった経緯をYに聞いてみた。
——————————————— 以下がYからの返事 ———————————————–
自分が所有してきた1989年式ポルシェ911カレラ4(964-5MT)と2001年式BMW330iMスポーツ(E46-5AT)での経験から、車を安心して且つ思いっきり使って遊ぶには以下の点を決めています。それをルーテシアを所有してからも実行してます。
・エンジンはノーマルで調子よい状態を保つ(無理に改造しない)。そのためには、良い空気(ノーマルのエアクリーナー)、良い電気(プラグ・バッテリーや充電を健全に)、 良い燃料(インジェクターも健全に、時にはしっかり全開にしてガソリンをしっかり噴射する)の3ポイントを意識してます。
・その次に、YRSのオーバルスクール、オーバルレースでの経験から、エンジンマウントやミッションマウントの健全性が重要であるということ。マウントが弱っていると、横Gがかかった時にシフトが入りにくいです。また加減速時にエンジンが「どっこらしょ」と動くというか、妙な振動やもっさり感・ピッチングが感じられるからです。(YRS参加者の動画でもコーナー中にシフトレバーが勝手に動くほどエンジン・ミッションにGがかかっているのが見てとれましたので)
このことから、「マウントはいつ交換しようかな?」とは車を購入する前から考えていました。ディーラーで質問したところ
・エンジン側マウントはタイミングベルト交換時ならついでの作業なので工賃が割引。
・ミッション側マウントはクラッチ交換時ならついでの作業なので工賃が割引。
と有益な情報を教えていただきました。
ですので、これにならってメンテナンスしているというのが今回ミッションマウントを交換した背景です。
私のルーテシアでは、エンジンマウントの交換 → アイドリング時のブルブル振動が激減(効果大でした)。
ミッションマウントの交換 → クラッチ交換の効果の方が大きいと思いますが、シフトのフィーリングが良くなりました。
——————————————— 以上がYからの返事 ———————————————–
なるほどね。ワタクシの終の相棒はそれほど走っていないけど、時間は経過しているから気にかけてやらないといけないね。

しばらく前に数字がそろったと言ってYが送ってきた画像
ホント
クルマって丈夫なんだなとつくづく思う
しっかり使ってあげるのがいいのかもね
長生きしなきゃ ‼ 相棒のためにも