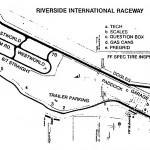第70回 アイドリングストップ

掲載が遅れてしまったが、筑波サーキットで開催したエンジンドライビングレッスンに岡崎市から駆けつけてくれたTさんのウインドと
* * * * * * * *
トゥィンゴ ゴルディーニ ルノー・スポールを点検に出した。お世話になったのはルノー京都。今回は代車に新車のマーチを貸してくれた。そして、これがアイドリングストップの興味津々初体験。
と言っても、アイドリングストップ自体は何年も前から実用に供されている技術だし、町を走ればアイドリングストップバスが青信号になってエンジンをかけて(?)発進するのを目にするし、スクールに来たアルファロメオジュリエッタのStart&STOPシステムをパドックで試させてもらったこともあるから、興味の対象はもっぱら、アイドリングストップ付きのクルマを日常的に乗った時に自分がどんな反応をするか、だった。
マーチのアイドリングストップはスイッチの切り替えでで機能させないようにできること、アイドリングストップ中にステアリングを動かすとアイドリングストップが解除されることを教えてもらい、ちょっと安心して八条通りに乗り出した。
で、結論から言うと、「アイドリングストップという技術は確かにクルマの進化として認められるけど、違和感を感じることは避けられない」だった。
誤解のないように付け加えておくと、マーチのアイドリングストップのことを行っているのでは決してない。自宅から御殿場インターチェンジまでの400キロ強の間に信号機がひとつしかないユーザーにとってアイドリングストップが有益なのか、という議論をするつもりもない。
「アイドリングストップ機能がついていれば排気ガスの排出が減って環境にやさしく、燃費性能も向上するのでおさいふにもやさしい」と、あたかも排気ガスをたれ流すクルマが悪者で、アイドリングストップ装着車が善人だと言わんばかりの売り方に疑問を感じるのだ。そう。短期間ながら自分で体験して、今までもやもやしていたものが晴れた。技術そのものは拍手ものなのだが、もやもやの原因はその技術の伝達の仕方だった。
自動車技術として燃費向上を図るのでであればエンジン内部や駆動系の開発によってそれが達成されるべきであろうし、短時間エンジンを停止するという対症療法的な方法で声高に数値の改善を謳うのはいかがなものか、という話だ。使う環境によっては乗り手の利便性が大いに高まるのだから、もったいない話だと思う。
アイドリングストップ付きのクルマに乗っていてもその効能にあずかれない人もいる。アイドリングストップ自体を嫌う人もいるだろう。逆に、カタログに書かれた数値だけを比較して、個人の嗜好を抑えてアイドリングストップ装着のクルマを選んだ人がいるかも知れない。
やはり、この手のデバイスは、特にアイドリングストップに関しては「アイドリングストップという技術を搭載しています。通常の走行では特別に意識していただくことはありません。ただアイドリングストップを行うことで環境への負荷を減らすことはできます。機会があればそんな運転を試されてはいかがでしょう」というようなメッセージと『対』になるべきものだと思う。
ある日。スタッフで食事をしている時に絶対にぶつからないクルマの話になった。レーダーが人間の代わりをして障害物の手前で完全に停止させるデバイスを内蔵したクルマだ。一度試乗会に行こうかということになりあるスタッフが言った。「トムさんなら絶対にぶつけてみせるでしょ」と。「もちろん」と答えた。冗談だが、その場に居合わせたみんなが、クルマは安全な乗り物ですというイメージだけが一人歩きしなければいいがな、と願っていた。
その昔。米国日産が『Z』をアメリカ市場に投入するにあたりCMを流した。サーキットをさっそうと走るZの姿が目に焼きついたころ「You own the road]という刺激的な文字が現れる、そんなCMだった。が、そのCM、1週間もしないうちに画面から消えた。NHTSA(運輸省道路交通安全局)がユーザーに誤解を生じさせる可能性があるとして、放映の自粛を勧告したからだった。
アメリカと比べると概して日本のマスコミは、CMを含めての話だが極めて情緒的だ。クルマは乗り手の人生を増幅させる側面を持つから、メーカーもマスコミも情報の伝達方法には合理性を軸にして気を配るべきだと考える。も少し配慮があれば、喜んで技術を享受する人が増えると思うのだが。
ま、クルマが今よりもずっとプリミティブが機械であったころから運転の楽しさを追い求めてきた人間にとっては、最近のクルマの動きを制御するデバイスに馴染めないというか、おせっかいだとすら思ってしまう。
時代を考えれば最新技術に身を任せられるようにならなければならないとは思うのだが、クルマに任せたゆえに起きた悲惨な出来事をたくさん知っているし、任せたとたんに自分の運転が下手になってしまうような気がするし、運転に対する緊張感が薄らぎ老け込むような気がして、いまだにこの手のデバイスを受け入れるのが難しい。
話が横道(?)にそれたけど、グランドオープニングの招待状をもらっておきながらなかなか行けなかったルノー京都CADONOにおじゃました。

外には納車待ちのトゥィンゴ ゴルディーニ ルノー・スポールが1台
まぎれもなくこの日のルノー京都CADONOはルノー・スポール占拠率が極めて高く、こんなディーラーがたくさんあればナ、と思わずにはいられなかった。
そんなディーラーでユイレーシングスクールの座学をやってみたい!